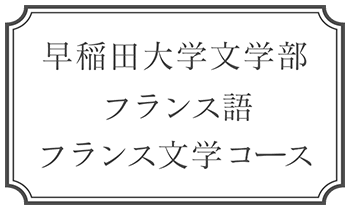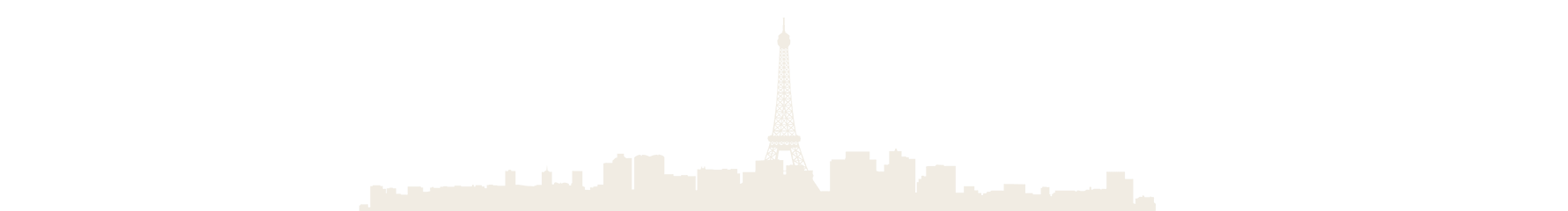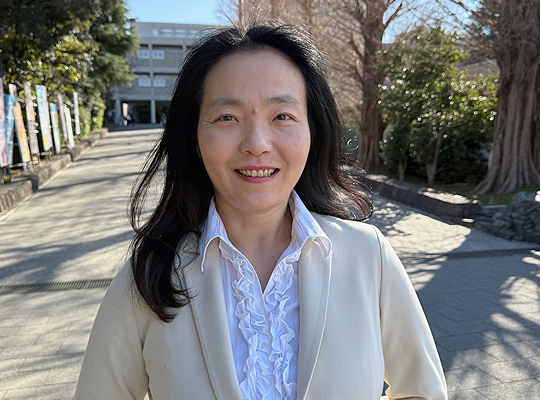
井上 櫻子 教授
【略歴】
2000年
京都大学文学部フランス語
フランス文学専修卒業
2002年
京都大学文学研究科フランス語
フランス文学専修修士課程修了
2002〜2005年
パリ第4大学に留学(DEAおよび博士課程)
2005年
パリ第4大学博士課程修了
2006年
京都大学文学研究科フランス語
フランス文学専修博士課程研究指導認定退学
2006〜2007年
京都大学文学研究科COE研究員
同志社大学、関西学院大学、神戸女子大学、
神戸女子短期大学にて非常勤講師
2007〜2012年
慶應義塾大学文学部助教
2012〜2022年
慶應義塾大学文学部准教授
2022~2025年
慶應義塾大学文学部教授
2025年〜
早稲田大学文学部教授
──研究内容
大学に入ったときから、文学と哲学の両方に関心があり、専修(早稲田大学文学部でいうところのコース)選びにはかなり迷いました。さんざん悩んだ挙句、まずは大学入学後に学び始めたフランス語の力を高めつつ、少し時間をかけてやりたいことを見つけようと思って、フランス語フランス文学専修に進学することに決めました。フランス18世紀を代表する思想家にして作家、ジャン=ジャック・ルソー(1712-1778)を卒業論文と修士論文の研究テーマとしたのは、文学を選ぶか、哲学・思想を選ぶかという問いに、結局答えを出せず、むしろ双方の分野に関する知見を広めたいと考えた結果とも言えます。その後もルソーにおける感受性の問題に注目しながら、彼の人間論と文学作品との関連について考察を進めているのは、こうした経緯と無関係ではありません。
博士課程進学以降は、ルソーから視野を広げて、同時代の詩人たちの活動についても調査をおこなっています。フランス文学史上、ルソーは自然の美を発見した人物とされてきましたが、実際にはルソーが小説や自伝的著作を執筆していた時期に、四季の変遷とともに移りゆく自然の姿とそこに生きる人間の情緒的経験を歌い上げる詩人たちが次々と登場していたのです。こうした詩人たちの作品の中でも私が特に興味深いと感じたのが、ジャン=フランソワ・ド・サン=ランベール(1716-1803)の詩集『四季』(初版1769年)です。サン=ランベールは、アカデミー・フランセーズの会員に選出されるなど、生前高く評価された文人ですが、その功績は時の流れとともに忘れ去られてしまいました。しかし、ヴォルテールやルソー、ディドロといった思想家たちと親交があったサン=ランベールの作品は、韻文でありながら、人間の本性、そして事物の本性に迫ろうとする哲学的野心に貫かれています。サン=ランベールの作品を同時代の思想家の著作と関連づけながら読み解くことで、「18世紀は哲学の世紀であり、詩的精神は死滅した」というフランス文学史の定説に修正を迫ることができれば、と考えています。あわせて近年は、サン=ランベールが匿名で『百科全書』に寄稿した項目群の典拠研究も進めています。
18世紀研究と並行して、アナール学派の歴史家たちの論考を翻訳する作業にも長く携わってきました。博士論文を書き終えて間もない時期に、私をこの世界に誘ってくださったのは、ブローデルの大著『地中海』の訳者として知られる南山大学名誉教授の故・浜名優美先生です。若い研究者に活躍の機会を与えることを大切にされていた浜名先生のお姿を心に刻みつつ、先生の母校である早稲田で研究教育活動に勤しみたいと思います。
──主な著書・訳書・論文
【著書】
・« Influence de Burke dans Les Saisons de Saint-Lambert », Alain Génetiot (dir.) , L’Éloge lyrique, Presses universitaires de Nancy, 2008, pp. 259-271
・「『新エロイーズ』—パトスの解放を希求する「貞淑な」女性の物語—」、桑瀬章二郎編『ルソーを学ぶ人のために』、世界思想社、2010年、pp. 94-116
・「ルソーの『告白』における夜明けの光景と描写詩」、吉川一義、田口紀子編『文学作品が生まれるとき 生成のフランス文学』、京都大学学術出版会、2010年、pp. 83-101
・「文学作品の誕生と読者」『フランス文学をひらく テーマ・技法・制度』、慶應義塾大学出版会、2010年、pp. 193-206
・Jean-François de Saint-Lambert, Les Saisons. Poème, texte établi et annoté par Sakurako INOUE, STFM Classiques Garnier, 2014
・「サン=ランベールと『百科全書』—項目「メランコリー」を中心に」、逸見龍生、小関武史編、『百科全書の時空 典拠・生成・転位』、法政大学出版局、2018年、pp. 281-297
・「アベ・プレヴォー『マノン・レスコー』」、「ジャン=ジャック・ルソー『孤独な散歩者の夢想』」、「ファム・ファタルとオム・ファタル」、永井敦子、畠山達、黒岩卓編著『フランス文学の楽しみかた ウェルギリウスからル・クレジオまで』、ミネルヴァ書房、2021年、pp. 38-39、pp. 44-45、pp. 206-209
・「ポウプ、コラルドー、そしてルソー—『新エロイーズ』における感受性の諸相」、小川公代、吉野由利編『感受性とジェンダー <共感>の文化と近現代ヨーロッパ』、水声社、2023年、pp. 157-178
【訳書】
・フェルナン・ブローデル『ブローデル歴史集成III、日常の歴史』(共訳者として参加)浜名優美監訳、藤原書店、2007年
・セルゲイ・カルプ編『十八世紀研究者の仕事 知的自伝』(共訳者として参加)中川久定、増田真監訳、法政大学出版局、2008年
・E. ル=ロワ=ラデュリ、A. ビュルギエール監修『叢書「アナール 1929-2010」 歴史の対象と方法』全5巻(共訳者として参加)E. ル=ロワ=ラデュリ編、浜名優美監訳、藤原書店、2010-2017年
・ジャック・ル=ゴフ『中世と貨幣 歴史人類学的考察』藤原書店、2015年
・アントワーヌ・リルティ『セレブの誕生 「著名人」の出現と近代社会』(松村博史氏、斎藤山人氏との共訳)、名古屋大学出版会、2018年
・ジャン・スタロバンスキー『告発と誘惑 ジャン=ジャック・ルソー論』(浜名優美氏との共訳)、法政大学出版局、2019年
【論文】
・« Saint-Lambert contre Rousseau — la fonction des réflexions sur le théâtre dans Les Saisons — »,『フランス語フランス文学研究』日本フランス語フランス文学会、88号、2006年、pp. 27-42
・« La tradition de la poésie pastorale et l’anthropologie dans Les Saisons de Saint-Lambert — à propos de la sensibilité et de la jouissance — »,『フランス語フランス文学研究』日本フランス語フランス文学会、89号、2006年、pp. 30-44
・« Des Lumières au romantisme : autour de L’Imagination (1806) de Jacques Delille », Revue d’Histoire littéraire de la France, année 111, nº 3, 2011年, pp. 593-604
・« Jean-François de Saint-Lambert, lecteur et collaborateur de l’Encyclopédie : autour d’une note sur ‹ l’Été › des Saisons »,『「百科全書」・啓蒙研究論集』『百科全書』研究会、2号、 2013年、pp. 115-130
・「サン=ランベールの道徳思想―『百科全書』項目「利益 «INTÉRÊT» (Morale) 」の典拠研究―」、『慶應義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学』慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会、65号、2017年、pp. 55-66
・« Saint-Lambert, de l’article « Luxe » aux Saisons », Revue d’Histoire littéraire de la France, 117e année, nº 3, 2017年, pp. 521-527
・「サン=ランベールと『百科全書』―項目「作法« MANIÈRE »」をめぐって―」、『慶應義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学』慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会、67号、2018年、pp. 19-32
・「サン=ランベール、モンテスキュー、そしてエルヴェシウス―『百科全書』の項目「名誉 « HONNEUR » 」を中心に―」、『慶應義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学』慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会、70号、2020年、pp. 95-106
・「エルヴェシウスとサン=ランベール
—『百科全書』項目「立法者 « LÉGISLATEUR »」をめぐる一考察—」『藝文研究』慶應義塾大学藝文学会、124号、2024年、pp. 79-90 (pp. (141)-(152))
──専門以外に興味のあること
クラシック音楽です。中高生のころは、ピアノの練習に明け暮れ、ある時期までは、本気で音楽大学に進学したいとも思っていました。音楽の勉強をする夢(という名の無謀な野望)をあきらめて、大学でフランス文学の勉強をしてみようと思ったきっかけの一つに、当時、吉田秀和の音楽評論を愛読していたことが挙げられます。彼のエッセイには、「この曲の魅力をどのように言葉にすれば良いのだろう」と思案する者に、「あなたはきっとこのように言いたいのではないですか」と語りかけてくるような温かさがあるように感じていました。その吉田秀和が東大の仏文科卒であることを知り、フランス文学の勉強をすれば、自分なりに音楽の美しさを言葉にする力が身につけられるかもしれない、と(これまた無謀にも)考えたのです。
それから30年ほど経って、10代のころのように毎日ピアノに向かうことはなくなり、音楽はもっぱら聴くだけになってしまいました。ただ、大学入学後にフランス文学のみならず、広くヨーロッパの文化や歴史について学んだことで、クラシック音楽のさまざまな傑作が生まれた時代背景についても理解が深まったと思います。数年前に、ある語学雑誌にオペラやバレエについてのエッセイを寄稿する機会に恵まれたのは、私にとっては幸いなことでした。
──学生へのメッセージ
大学に入学すると、履修する科目の選択から始まって、高校の時よりも「個人の自由な判断」が認められるようになります。その結果、さまざまな場面で決断に迷う機会が増えるかもしれません。けれども、決して迷うことを恐れないでほしいと思います。迷うということは、目の前に無限の可能性が開かれていることだからです。時には回り道と思えることも、あとから振り返ってみれば、新たな発見や確信に至るまでの最初のステップだったということも少なくありません。
そして、どんな時であっても、その日その日を大切にしてほしいとも思います。フランス・ルネサンスを代表する詩人ピエール・ド・ロンサール(1524-1585)のある作品には、「生きなさい(……)明日を待ってはなりません。/今日から人生の薔薇を摘みなさい。 Vivez […] n’attendez à demain / Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.」という一節があります。これは、古代ローマ詩人ホラーティウスの「その日を摘めCarpe diem」という詩句を変奏したものです。宗教戦争による混乱の世に生きたロンサールの心に、ホラーティウスの言葉はどのように響いたのでしょうか。いずれにせよ、2人の詩人たちの言葉は、21世紀に生きる私たちの心にも訴えかける普遍的な教えのように思われます。