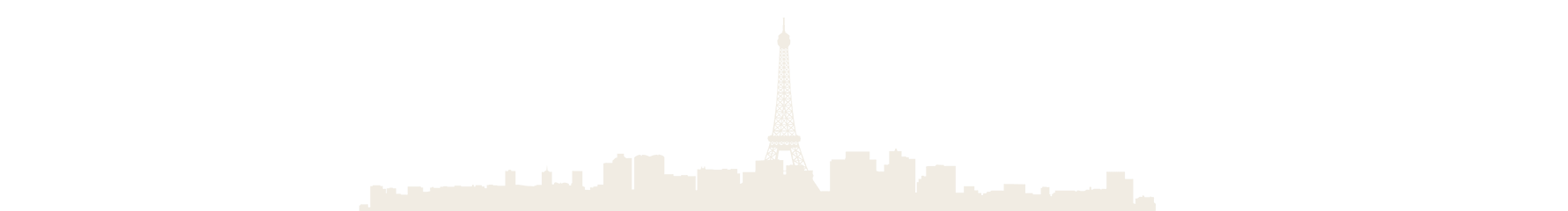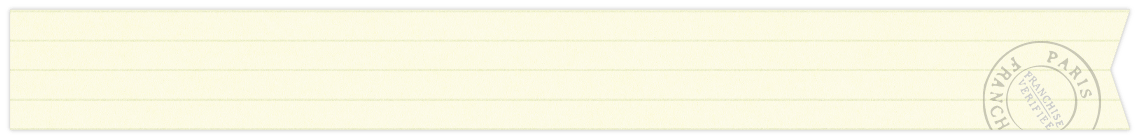
モントリオールのコリアン
片山 幹生
2013年7月末から8月にかけての3週間、私はケベック州政府が主催するフランス語教授法の研修に参加するため、モントリオールに滞在した。カナダのケベック州の人口は約800万人で、その8割はフランス語話者であり、州の公用語はフランス語である(カナダは州ごとに公用語が定められている)。モントリオールはケベック州最大の都市で、フランス語ではモンレアルと呼ばれる。
研修はモントリオール大学で行われ、日本人6名、韓国人3名、ラオス人2名の給費研修生の他、自費参加のケベック人1名、他の州からやってきた英語話者のカナダ人5名が参加していた。研修生はいずれもフランス語教育に携わる人間だったが、教えている対象は大学だけでなく、高校、小学生など様々だった。
私は韓国映画のファン、とりわけ女優ペ・ドゥナの熱心なファンであり、韓国人指揮者のチョン・ミョンフンを崇拝しているのだけれど、韓国映画やチョン・ミョンフンの音楽を知るはるか前の高校の頃から何となく韓国に興味を持っていて、パリでの留学先でも韓国人と親しくなることが多かった。日本、とりわけネットの世界では、反日や嫌韓がグロテスクに強調されることが多いけれど、私がこれまで知り合った韓国人は、情が厚くて、人なつこい、好奇心旺盛、礼儀正しく、繊細な気遣いがある、はっきり意思表示するといった性質を持っている人が多かった。今回のモントリオール大学の研修で出会った韓国人の先生方も私が持っている韓国人イメージそのままの気持ちのよい人たちばかりで、研修中には数度にわたって一緒に外出し、食事をとった。
今回の研修で親しくつきあった韓国人たちのなかでもとりわけ強い印象を残したのは、韓国系カナダ人のマリーさんだった。彼女は現在はカナダ国籍なので、正確に言えば韓国人ではないのだが。15年ほど前に夫と子供二人でカナダに移住し、オンタリオ州にあるカナダ最大の都市、トロントに住んでいる。上の子供はもう働いていて、下の子供は高校生だとのこと。マリーさんの年齢はおそらく私と同じくらい、40代半ばかあるいはもうちょっと上ぐらいだと思う。研修ではよく発言し、質問する人だった。教室外で最初に彼女と話したのは、モントリオールの花火大会に出かけたときである。研修の授業中にモントリオールの花火大会の話が出て、そのときに彼女はクラス全員に花火大会へ一緒に出かけないかと提案したのだ。この花火大会には結局、日本人5名(私を含む)、韓国人1名、そしてマリーさんで一緒に行った。花火会場に行く前に、夕食を一緒にとったのだが、そのときの雑談で彼女が15年ほど前に家族でカナダに移住した移民一世であることを知った。
「カナダへの移住は、大きな決断だったでしょうね?」と尋ねたとき、
「いいえ。移住を決めたときには、私はそれが大きな決断だとは思っていませんでした」
と彼女はさらりと答えた。夫が移住を決めて、彼女も反対することなくそれに従ったと言う。
自分には予想外だったこの返答に私はなぜか感動を覚えた。
あとになって平田オリザの『その河をこえて、五月』という演劇作品を思い出した。日韓交流事業の記念公演として2002年に新国立劇場で初演されたこの作品は、ソウルの語学学校を舞台としている。韓国人と在日コリアン、日本人留学生とのコミュニケーションが描かれたこの作品では、当時の韓国の若い世代のカナダ移住について言及されていた。マリーさんがカナダに移住したのはちょうどこの作品が初演された時期と重なっている。