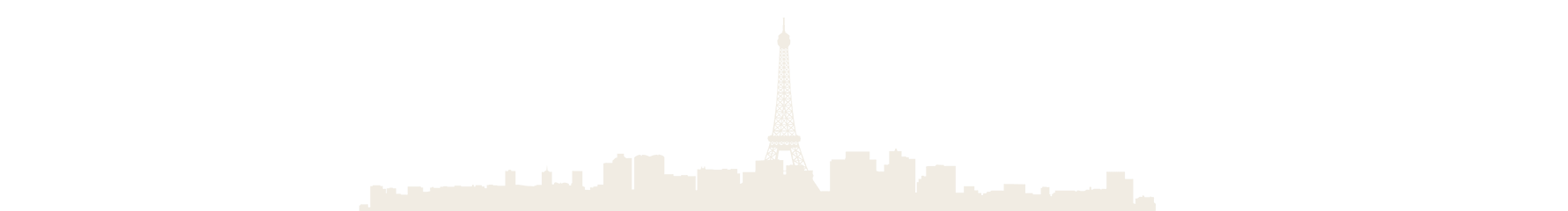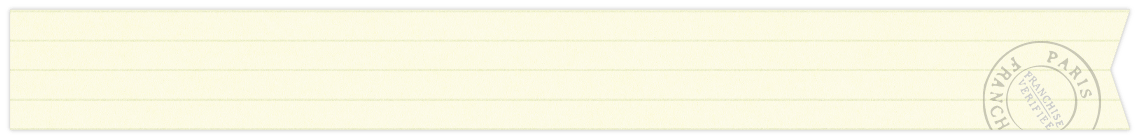
フランス語マンガとわたし
中島 万紀子
わたしがフランス語のマンガ(bande dessinée francophone)と出会ったのは、小学生時代にさかのぼる。日本でおそらく一番有名なフランス語マンガ(フランス「の」マンガ bande dessinée française と書かないのは著者のエルジェHergéがベルギー人だからだ)『タンタンの冒険旅行 Les aventures de Tintin』シリーズの翻訳が出はじめていたのだ。
日本のマンガとちがって粛々と単調にすすむコマ割りや、1ページの文字数の多さには一瞬ひるんだが、読み出したらたちまちのうちに引きこまれた。読み終わってフトわれに帰ると、この薄さで(だいたい1巻が45~60ページ程度)あれだけの奥行きと広がりをもてるとは……と毎回びっくりしたものである。
中学校でも、図書室にシリーズがそろっていたこともあって、同級生の間でタンタンはさりげなく流行っていた。授業中こっそり読んでいるけしからん輩もいたが(わたしではないです、念のため)版が大きいので(A4サイズ)こっそり読むにはなかなかの技術を要したようである。しかしそこまでしても続きが読みたいという気にさせるストーリーテリングの巧みさには、大人になった今でも感心させられる。あとは脇を固めるキャラクターの多彩さとおかしさがあげられよう。タンタン自身は、誤解を恐れずに言えば「主人公」によくある「いい子だがカラッポ(これといった個性もない)」というタイプだが、意外にナマイキな口をきく愛犬ミルー Milou(邦訳ではスノーウィ)、船乗り言葉の悪態をつきまくるアドック(ハドック)Haddock船長、へまばかりの刑事コンビDupontとDupond(邦訳ではデュ「ポ」ンとデュ「ボ」ン)、耳が遠くて話がことごとくとんちんかんになるトゥルヌソルTournesol(邦訳ではビーカー)教授といった人たちのやりとりがたまらなくおかしく、タンタンシリーズの白眉はこれだ!と思わされるほどである。
大学に入ってフランス語を学びはじめたわたしは、タンタンの原書を辞書を引き引き読んだりするようになった。そして大学3年で行った夏休みの語学研修で、人生で二つ目となる気に入りのフランス語マンガとの出会いを果たしたのである。フランカン Franquin(彼もまたベルギー人だ)作の『スピルウとファンタジオ Spirou et Fantasio』のシリーズだ。本屋でパラリと見たその絵柄のポップなかわいらしさに、わたしは完全にまいってしまった。ちなみに『スピルウとファンタジオ』シリーズは、ほかのマンガ家の手になるものもあるのだが、わたしはフランカンのものが一番好きで、さらにはフランカンの作品の中にはのちに描かれたもっと有名な『ガストン・ラガッフ Gaston Lagaffe』のシリーズもあるけれども、その頃になるとフランカンの線も熟達のデフォルメがされすぎている気がして、わたしはやっぱり、フランカンでは『スピルウとファンタジオ』が、『スピルウとファンタジオ』ではフランカンのものが一番好きである(のちにちゃんと読んでみたら『ガストン』もかなりおかしかったことを、念のため申し添えておきます。緑のトックリセーターを着ているが腹とヘソがいつも見えていて、ネコとカモメを飼っていてへまばかりしているものぐさな男子の話だ。これだけでもすごいでしょう)。タンタン・シリーズのある種端正なやわらかい線とはひと味ちがう、緩急と躍動感に富んだその頃のフランカンの線を見ていると、ただならぬ高揚感をおぼえたものだ。なぜかいつもベルボーイの赤い衣装を着ているスピルウ(彼も「主人公」らしくちょっとカラッポなキャラクターだが)と、お調子者のファンタジオのコンビぶり、いや、そうそう、忘れてはならないリスのスピップ Spipとのトリオぶりも楽しい。あまりにも気に入ったので、語学研修の終盤のある日、パリのフナック Fnac(本屋)でありったけの単行本を買い、その足で郵便局へ回って日本の自宅宛に発送した。郵便局で狂ったようにマンガを箱詰めしている東洋の謎の女子を見ていぶかしく思ったらしいお爺さんに話しかけられたのもなつかしい思い出だ。気に入ったコマを12選び出してコピーして、自分だけのまさに「オリジナル」な「スピルウとファンタジオ・カレンダー」を作り、部屋に飾ってひとり悦に入ったりしていたことも今急に思い出した。なんともヒマだったことである。