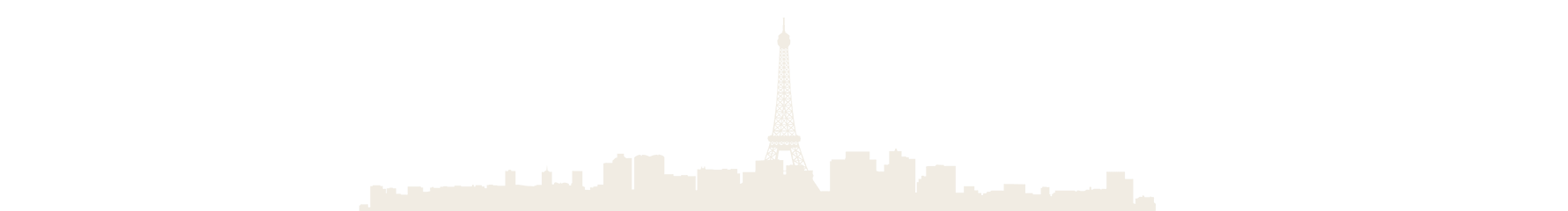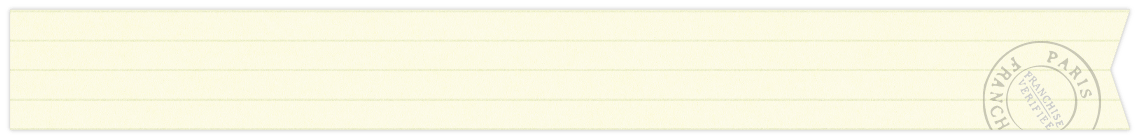
スイス・アパート メント
小出石 敦子
まだ六年も経っていないのに、随分昔のことのように思える。いや、いったいあれは本当のことだったのかとさえ思えるときがある。私のスイス留学のことだ。留学といえば、未知の国、未知の人々との出会いであるし、日本では経験できない「何か」が待っているような、不安とそれ以上に期待に胸を高鳴らせる経験であるはずだ。たしかに、初めてスイスに旅立ったときの私は、もっと若かったし、心逸る思いだった。長く付き合える異国の友に出会い、心踊ることがあったのもその時だ。だが二度目となるとそうもいかない。もちろん、博士論文完成のために、読むべき文献の山山と歩むべき長い道のりが、湖の彼方で雄大に聳えるアルプスの山山や、カウベルをならしつつ牛たちが長閑に草を食む草原のイメージよりも、重く心にのしかかっていたからには違いない。スイスに向けて日本を離れるときの私の心境は、「行きたくない」であった。そして日本に戻ってきたときの感想は「やっと終わった」だ。これではさぞ辛い留学生活であったろうと想像されるが、スイスにいた四年と九ヵ月、実は淡々と日々を過ごしていた。今振り返ってみると、その歳月は、苦労して手に入れた学位記の紙片同様、薄っぺらで厚みがなく、いくつかの情景のイメージの断片として記憶されている。これが、正直なところ、四年九ヵ月にわたるスイス留学が私に残したものである。
今日はこのイメージの断片のいくつかをお話しする。ある青年と娘についてである。私がスイスで暮らしていたアパートの住人だ。といってもそれは、恋慕の情によって美化される恋人の面影のように心を酔わせるイメージでも、誰もいない暗い夜道で突然車のライトに照らし出されたときのような鮮烈なイメージでもない。それは、何でもない日常のほんの一瞬をそのままファインダーにおさめた写真のようなもので、普段は押入れの奥にあって、たまに大掃除をするために、雑然と詰まれたガラクタどもを掻きわけたとき、あの少し色褪せた状態で見つかる写真である。何でもないイメージだが、たしかにこんなこともあったなという気持ちにさせるイメージなのだ。