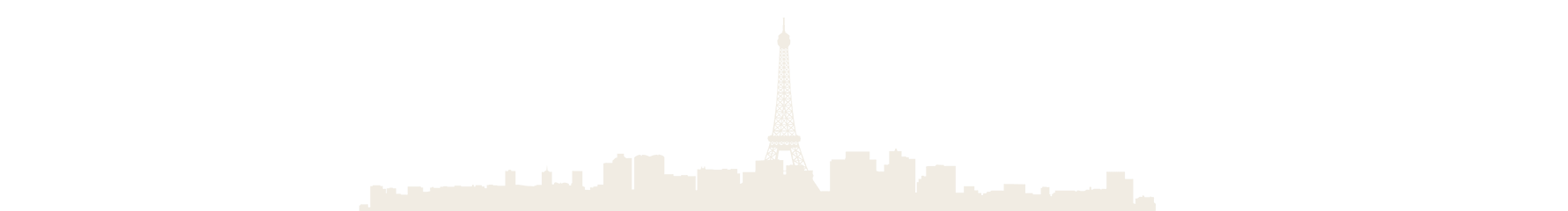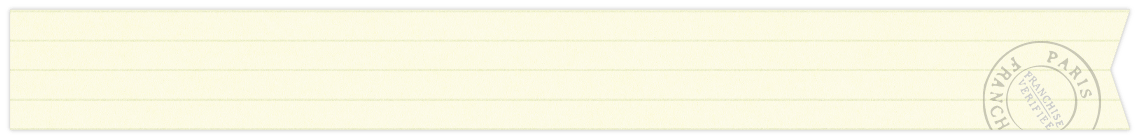
スイス・アパート メント
この時の私は凄かった。もう管理人では埒が開かないので、建物のオーナーに直接電話をかけ、クラッカーを窓から投げ捨てる危険な人物を、どうにか追い出してくれとまくし立てた(そのときの私のフランス語は神がかり的に流暢だった!)。翌日オーナーが直接青年の所に来て話をしたということを、わざわざ電話を寄こして話してくれた。これ以降、青年は少し大人しくなったように思う。しかし、私ももう論文の大詰めで他のことなど構っていられず、詳しい事後報告も受けていないので、私がアパートを引き上げた後、あの青年がどうなったのか、全然知らない。立ち直っているのか、それとも今もドラッグに依存し、犬を虐待し、空き巣を続けているのだろうか。
ご覧のよう に、私の二度目のスイス留学においては、『スパニッシュ・アパートメントL’auberge espagnol』(セドリック・クラピッシュ監督)のような、甘酸っぱい留学時代の青春の一コマを想起させるものはまるで存在しない。それなのに時折、あの青年やあの黒人娘の顔が、記憶の彼方からふと立ち現れることがある。恋が一種の心の傷であるならば、私の出会った二人も、その死や暴力によって、私のvie生にある種の傷をつけたのだ。それなのに、私の記憶の中の彼らは、泣き喚き、泡を吹いて倒れている姿でも、恐ろしい形相で犬を折檻し、ドラッグの酔いに任せてクラッカーを投げつける不敵な顔でもなく、ただそこに、ネグリジェ姿で佇み、あるいは寂しそうに犬と寄り添っている姿なのである。その姿を思い出すとき、私は怒りも苦痛も哀れさえも感じない。時間の作用によって、感情の厚みがすべて消し去られてしまったのかもしれない。感じるのは、ああ、たしかに私は、同じ時期に、同じアパートで暮らしていたのだな、彼らと、ということだけである。もしあの娘にもう一度会うことが叶うとしたら、またスイスに戻りたいと思うだろうか?穏やかに澄んだレマン湖のあの町に?しかし、来る日も来る日も薄暗いランプの下、本のページを繰っていたあの頃に?何とも私には答えられそうにない。