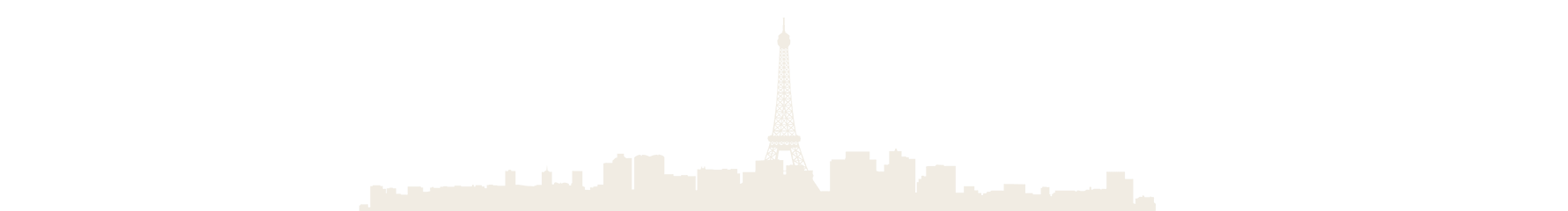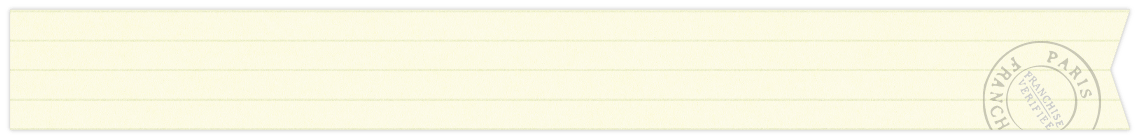
龍の名前
*
中村**にはかなり年の離れたお姉さんがいて、たしか美大に通っていたのだと思う。彼の部屋にはマグリットやダリの大きな画集が何冊も置かれてあり、だから僕は小学生のときに、すでにシュルレアリスムという言葉を知っていたはずだ。具体的な作家名は覚えていないが、彼自身が一番熱心に読んでいたのは何か観念的なSF小説のようなもので、さすがにブルトンやアラゴンを読んでいたわけではないだろう。だがそれでも彼の文学的な嗅覚はきわめて早熟だったに違いない。おそらくは中学生になった頃のある日、彼の家に行くと本棚に見慣れない美しい装幀の本があり、この題名は何と読むのかと聞くと、「『めだまだん』でしょう。他に何て読むの?」と言う。でも一体何の本なのか?「まあ、いわゆるエロティシズム小説だよ。」しばらくして、当時渋谷の西武デパート地下にあった「ポルトパロール」で同じものを見つけ、棚から取ってどんなものかと読み始めてみたものの、どうしていいかわからずに棚へ戻したのを覚えている。
その頃からいくらか日本の現代詩を読んではいたけれど、中学を卒業するまでは爬虫類学者になるという僕の決心が揺らぐことはなかったし、おそらく中村**とも共有していた感じ方なのだと思うが、文学関係の何かを職業にするというのはどうもスマートではないように思われた。想像力に関するすべては職業という義務から解放されてあるべきだった。だから僕は、高校に入って次第に文学系の研究をするという可能性も考えはじめた頃も、彼と会うのをやめるまで、その気持ちをはっきりとは口にしなかったと思う。
*
彼と会わなくなったのは突然だった。あるとき彼は、君はこんな風に僕と会い続けていても、もう何も得ることはないんじゃないかと尋ねた。そう尋ねられたのに対して、友人関係というのは得るものがあるなしの問題ではないといった答をすることは、僕たちのあいだでは考えられなかった。またそう言われてみると、事実こうしていても何も意味がないようにも思えた。だからいかなる口論や特別な事件があったわけでもなしに、そのとき以来僕は中村**には会っていない。数年前久しぶりに出かけた小学校のクラス会のときも彼の消息は誰も知らなかったし、彼が今どこで何をしているのか、だから僕には何もわからない。
シュルレアリスムの研究者になったのが、彼のいる場所へ近づくためだったのか、むしろ遠ざかるためだったのか、僕には言うことができない。とりあえず、彼がこの世界に存在しなければそうなっていなかったことだけは間違いないだろう。だが彼は乗り越えるべき対象ではなかったし、もちろん共通の目標を持った同志でもなかった。ブルトンにとってのヴァシェのように、愛情の対象であったと言うこともできない。おそらく彼は「他者」であったと思う。大文字の他者とか小文字の他者とかでなく、単に一人の「他者」であった。僕が今も何らかの思考を生産し続けているとするなら、おそらく彼はそこにいる。そしてもし彼にそう告げたら、彼はそれを迷惑だと言うだろう。彼がどうしているかわからないのは、決して好都合なのではなく、端的に驚くべきことである。
*
留学中の、多かれ少なかれ自閉的な研究生活のあいだ、作品としてまとめるような意図は一切なしに、僕はいくつかのストーリーを考え出した。それらはすべてある森を中心とした小世界の物語なのだが、その世界では、恋愛以外のすべてを恋愛のために犠牲にすることだけが掟であった。設定の細部は覚えていないけれど、その登場人物の一人が、彼だけの秘密である竜の名を授けられていたことは間違いがない。彼は最終的に、互いに相手の生であり死であるただ一人の女性にその名を打ち明けるはずなのだが、竜の名をあからさまに発音してしまうのは何か単純すぎる結末のような気がしたし、ましてや一種のごまかしのように思えた。満足のいく解決が得られたわけではなかったが、考えた末に結局選び取った結末は、次のようなものだったと思う。彼は竜の名を口にはせずに、それを小さな紙に書き付けて彼女の前にかざして見せる。それは特別な文字で記されていて、幾通りかに読める名であり、彼女がそれを何と発音するものと考えたかはわからない。だが彼女はそれをしばらく見つめると、すべて悟ったような視線を彼に向けながら、紙を折りたたんで呑み込んでしまうのであった。ハッピーエンドとはおそらく、そうしたものであるしかないだろう。
僕が自分の竜の名を誰かに明かすことは、いつまでもないだろうと思う。