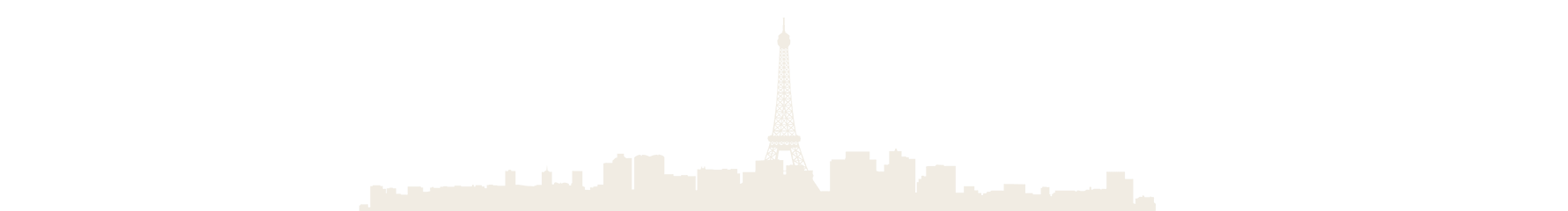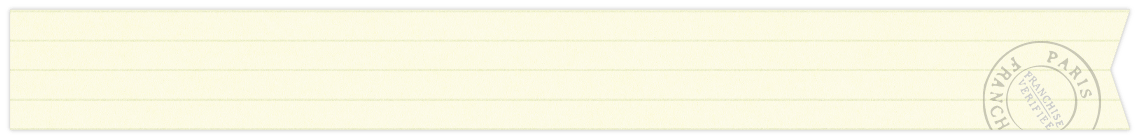
《専用》エレベーター
川瀬 武夫
「それを聞いて、なんという見事な問題解決法だろうとおれは思ったね」と、Kが感に堪えたような顔つきをした。Kとはもう10年あまりも前のパリ留学時代の仲間で、今回もたまたまそれぞれの勤務先の大学から1年間の研究休暇をもらって、こうして共に懐かしの都へまいもどってきたというわけである。
なにかにつけ目端のきくKは、パリに着いて数日もしないうちに、お屋敷街の16区に立派なアパルトマンを借り、まだ仮住まいのホテルにくすぶっていた私を呼んでくれた。今世紀初頭に有名な建築家のギマールが設計したという堂々たるアール・ヌーヴォー建築の、日本式にいえば4階にあるそのアパルトマンに私を招き入れると、やおらKがプラスチック製の黒いマッチ箱のようなものを掌に取り出して見せた。「ここに入居するとき、家主が鍵と一緒に渡してくれたものだよ。こいつは一種の発信装置で、これをチカチカやるとエレベーターが作動するという寸法だ」そういえば、さっき上がってくるとき、Kのやつが妙なことをしていたなと思いあたった。「たかがエレベーターひとつに、ご大層な仕掛けじゃないか。外部の人間には勝手に使わせないということか」「いや、眼目はそこじゃないんだ」Kが得たりとばかりに答えた。「家主の説明によると、ここのエレベーターは去年設置されたばかりのものだ。なんでもその費用分担の件で、ずいぶんと揉めたらしい。下の階に住む連中はそんなものはいらないというし、上の方の階にいても、年金暮らしで余分な蓄えのない老齢世帯は話にのらなかったそうだ。それで結局、有志のみが金を出すことになった。そうして彼らにだけこいつが配られたというわけさ」「すると、同じ建物に住んでいながら、エレベーターを使える人間と使えない人間がここでは差別されているというわけかい。これは小金持ちだけの専用エレベーターなのか」あまりの意想外のことにあっけにとられ、つい詰問口調になってしまったようだ。Kがきらりと目を光らせた。「まさか君まで、年寄りがかわいそうだの、弱者切り捨てだの、センチメンタルなお題目を並べるつもりじゃないだろうな。たしかに日本じゃ、決してこうはいかないさ。話がつかないままエレベーターの件はお流れになるか、さもなきゃ有形無形の圧力に負けて、なけなしの貯金を吐き出さされるのがおちだろう。こんな思いきった解決法は、誰も考えすらしないはずだよ。だが、いいかい。こうして金を払った者がはっきりと目に見える形で権利を保証される一方、払いたくなければその自由も当然のように尊重される。なんとも合理的で、明快なやり方じゃないか。おれはいまさらのように、フランスというのは本当に大人の国だと思ったね。それがおれには、この国に生活していて実に気分のいいところなんだ」
Kの意見に一理あることは認めざるをえなかった。曖昧な感情論に流されず、あくまでも理性的に問題解決にあたることこそ、まさに彼のいう〈大人〉の態度というものだろう。うわべは非情に見えることが、ある種の勇気であったりすることも分からぬではない。そして、われわれ日本人にとって、そうした態度をとりつづけるのが、いかに不得手であるかということも。
それでも、と私は思う。非情の産物だか、勇気の結果だか知らないが、とにかくこのエレベーターが作られるまで、ここの住人たちのあいだにもさまざまな心の葛藤があったのではないか。重たそうな買い物袋をさげて、狭い階段をとぼとぼと上がっていく老婆の後ろ姿を、いまでもなにがしかの辛い感情を込めて見送っている住人もきっといるにちがいない”"。
すでに夜も更けたので、私は釈然としないままKのアパルトマンを辞した。エレベーターの前に立とうとすると、Kが「ああ、忘れてた」といって私の肩ごしに例のチカチカをやってくれた。 鈍いうなり声をたてながら、〈専用〉エレベーターが上がってくる。
[付記]このエッセーは筆者の1993年度在外研究期間中にパリで書かれ、同年7月16日の読売新聞衛星版(ヨーロッパで発行)に「合理的過ぎる?解決法」という、あまりといえばあまりのタイトルを付せられて掲載された。今回の再録にあたってタイトルをオリジナルのものに戻した次第である。