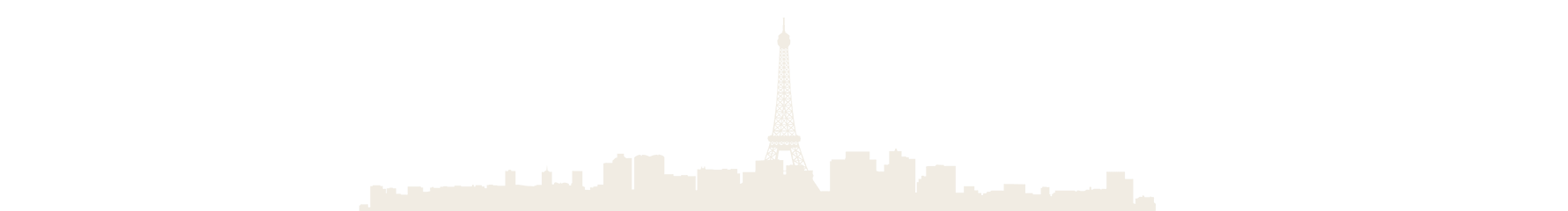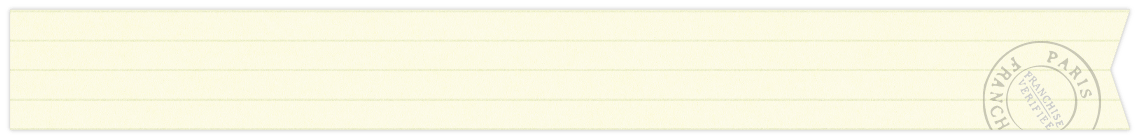
Que reste-t-il de nos amours ?
実際にもそうなった。この本に取り上げられた主なアーティストまたはグループ八組のうち、四組が活動を停止した、またはすることになっている。オクシタン音楽の一派コンパニー・リュバット・デ・ガスコーニャ、ユダヤ・アラブ音楽の大歌手リリ・ボニッシュ、フランス/マグレブの融合形グナワ・ディフュージョン、現代的なシャンソン・レアリストを追求したエスクロ。特にマグレブ系の退潮は著しく、グナワ・ディフュジオンの他にも、音楽と政治という面ではより重要な存在だったゼブダや、個人的にはかなり期待していたデゾリアンタルなどのグループが、次々に消えてしまった(その一方で、優れた研究書の出版が増えている。特に Danielle Marx-Scouras, La France de Zebda 1981-2004 : faire de la musique un acte politique と Bouziane Daoudi & Hadj Miliani, Beur’s melodies : cent ans de chansons immigrées du blues berbère au rap beur は興味深い)。
幕を閉じた時代、それはグループの時代だったことがいまにしてわかる。この15年間のフランスのポピュラー音楽は、数々の個性的なグループによって支えられていた。この時期より前に音楽の聞き方が定まった先輩方や、この時期にはまだ何も聞いていなかった後輩達にとっては、代表的な顔役不在のわかりにくい時代ということになるのかもしれない。しかしそれは、間近に生きた者にとっては混沌とした豊かさの時代だったのである。スターシステムに頼ることなく、創意に富んだ個人と個人が未聞の集団を結成し、創造的破壊と再編を繰り返した時代。それはまた、ヴァリエテ・フランセーズが芸能から芸術へと発展した時代でもあった。電子機器の利点をフルに活用しつつ、従来は作曲家や演奏者など専門家集団の専売特許だった奥行きのあるサウンドを我がものとした人々の表現は、芸術的革新の最前線へと躍り出たのだった。
そしていま。その表情は相変わらずはっきりしないまま、フランスのポピュラー音楽は、グループの時代から個人の時代へと移り変わろうとしている。個人といっても、二昔前のカリスマ的な個人ではなく、いくつかの要素を併せ持った、いわば多機能な個人だ。元トップ・モデルのカルラ・ブルーニや、映画関係から転身したベナバールや、エッセイストでもあるヴァンサン・ドゥレルムなど、音楽一筋ではないアーティストの活躍が目立っている。音楽的な面では、革新的な要素は特に見られない。長く音楽を聞いてきた者にとっては、フォーキーなテテや、英国風のジャンヌ・シェラルなど、むしろ懐かしいくらいだ。それでも、既存のスタイルをただ模倣したものでないことはわかる。彼らは彼らで、自分の耳に聞こえた音を素直に表しているのだろう。そしてそのような姿勢が、以前の豊かさを知らない世代にはむしろ好ましく感じられるのだろう。
時代の変化を別の角度から捉えると、サウンド優先から言葉重視の傾向が明確になったということ。それは、簡単 にいえば「9・11」以降の流れを受けたものだ。良くも悪くも浮ついた気分を出しにくくなった昨今のフランスでは、歌詞が生半可な歌は太刀打ちできない。率直で、凝っていて、人間的な感情に裏打ちされたものが前面に出ている(こうした一連の歌手を指して「ヌーヴェル・シャンソン(・フランセーズ)」と呼ぶ向きもある)。そして、この傾向を極端に押し進めたものと見られるのが、ここ数年で急速に展開した「スラム」の一派だ。スラムとは、コンテスト形式で競われるポエトリー・リーデイングの一種で、本来は音楽ではないのだが、最近では音楽を取り入れたスラムが大流行している。グラン・コール・マラードやスレイマン・ディアマンカ、またはラップ出身のアブダル・マリックの近作が素晴らしい。詳しくは拙稿「もう音楽は要らない? パリ郊外発<スラム>ムーヴメントの盛り上がり」『ラティーナ』2007年3月号をご覧ください。