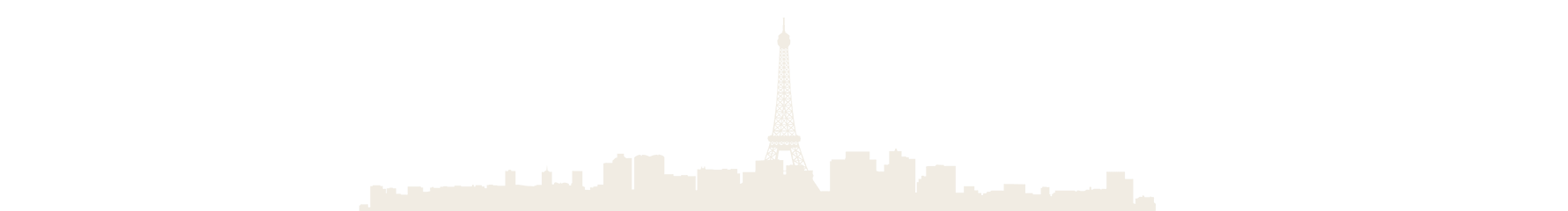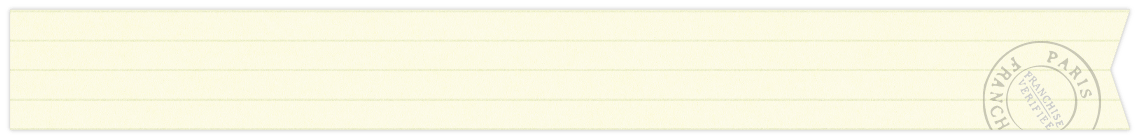
「マンガ」そして「ジャパニメーション」……
加倉井 仁
早稲田大学文学学術院のフランス語講師陣による「リレー・コラム」というコーナーの中で既に、中島万紀子先生が「フランス語マンガとわたし」というタイトルで、さらに、古永真一先生が「タンタンを聴く、着る、旅する」というタイトルで、フランス(語)の漫画というか、「バンド・デシネ(bande dessinée)」を題材にコラムを書かれています。
このコラムのタイトルを一目見てお気づきのように、僕も、「manga」と「japanimation」を叩き台に話をさせていただきます。「ワセダのフラ語の先生はどんだけぇマンガ好きなんだよ」とあきれないでください。
さて、最初に言っておきたいのですが「あえて言おう(元ネタが分かる人だけ笑ってください)、フランス(語)<の>漫画である『バンド・デシネbande dessinée』と『マンガ manga』はまったく別物である、と」。
こう言ってよければ、全ての面において<文法>が違うのです。物語の文法、コマ割りの文法、絵の描き方、「bandedessinée」と「manga」は別物なのです。そして今回このコラムで取り上げるのは後者の方です。
さて、「manga」という単語を聞いてすでにピンときた人もいると思うのですが、フランス語で「le manga / un manga」と言えば、日本語の「マンガ」と同じモノを指し示します。というか、そもそも日本語です。
僕は、2004年の9月から約二年間フランスに留学していたのですが、渡仏以前から、フランスでは日本の「マンガ」が流行っていると聞いていました。たとえば「Olive et Tom」というタイトルで『キャプテン翼』が翻訳され、アニメになっているとか(ちなみに、オリーヴが翼でトムが若林です。ネット上にはトムが岬くんという情報がありましたが、あれは誤りです)。とはいえ、フランスに行く前は話半分、日本のマンガやアニメなんてそれほど流行ってないんじゃないの、と思い込んでいたのです。
しかしパリに着いてビックリ。
ソルボンヌの近くにある「Gibertジベール」という本屋や、「Fnacフナック」という家電を中心にした量販店(僕のイメージではビックカメラやヨドバシカメラに近い……そのようなタイプのお店)には、日本のマンガのフランス語版が所狭しと置かれ、DVDのコーナーでは、ジブリ作品(その時は『魔女の宅急便』)が週間売り上げ第一位を占めていたような状況だったのです。
テレビでは、もちろんアメリカのアニメーションもやっていましたが、『ドラゴンボール』や『聖闘士星矢』といった日本のアニメ、いわゆる「ジャパニメーション」が多数放映されていました(ちなみに『頭文字D』をテレビで観た時には、こんな北関東の峠のカーバトルという題材をフランス人はどう受け取っているのか謎でした)。