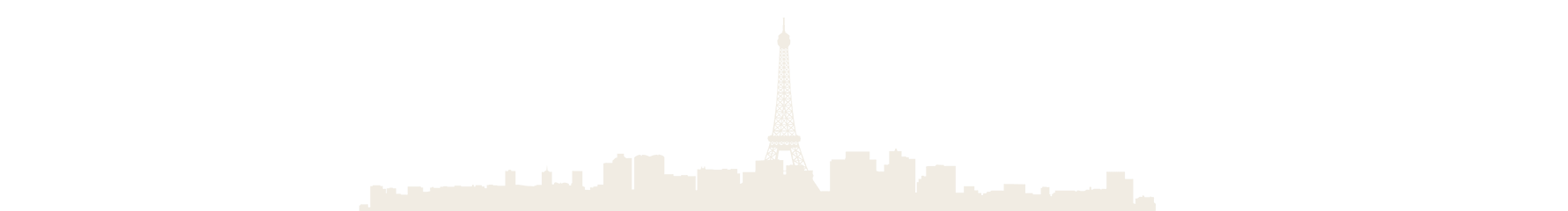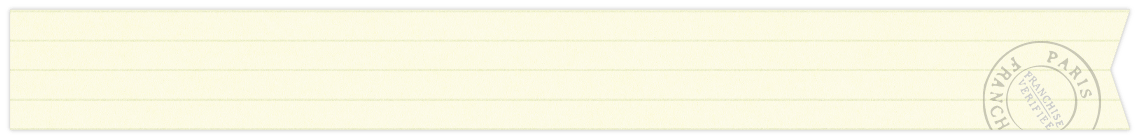
Paris, je t’aime について
次の場面は一転して、緑の豊かな公園。一面に陽光のふりそそぐ芝生の中を、おばさんは両手に紙袋をさげてゆっくりとした足取りで進んでゆき、ベンチに腰を下ろすとおもむろに紙袋からサンドウィッチを取り出す。まさにその瞬間、映像の何かが不意に僕の頭をガツンと打った。途方もなく懐かしい何かが視界をかすめたような気がした。間をおかずショットが切り換ってサンドウィッチを頬張っているおばさんのクロースアップ。そして朗読の声は、おばさんの身にも「何かが起こった」ことを伝えている。午後のうららかな日差しを髪先に受けながら、おばさんがうっとりとした眼差しで右手を見下ろすと、滑り台などの遊具で遊ぶ子供たちの姿が、左手に目を向ければ、小さな湖へとつづく斜面のところどころに腰をおろしている人々の姿がカメラに捉えられ、おばさんがさらに首を左に向けると、隣のベンチに腰を掛けている老夫婦の背後に、もう一度「それ」が画面に映った。プラタナスの巨木だった。溶岩流が地面から噴き出しそのまま凝固したかのような、ゴツゴツした樹皮をもつあの忘れようもないモンスリー公園のプラタナス。その近くの寮で過ごした1年半のあいだ、この公園を散策するたびに、僕はかならずその巨木に触れに行った。溶岩のような隆々たる幹の膚の、ちょうどしっくりくるような所に軽く手を添えて、何も考えずにしばらくその木陰に立つ。そして振り仰ぎ、見事な枝ぶりを、密な葉叢を透かして洩れでる光を、いつまでも見つめていた。
「ある感情がわきあがりました。まるでまったく知らない何かを思い出しているかのように、それとも、いつも待ち焦がれていた何かを思い出しているかのように。それは何だったのか。それは私が忘れてしまったことなのかもしれないし、私の人生にずっと欠けていたことなのかしれません。ただ言えるのは、私が悲しみと喜びとを同時に感じていたことです。でも、それほどの悲しみではありません。というのも、その時、私は生きていると感じていたのだから。そう、たしかに生きている、と」──こう作文が読み上げられながら、カメラはおばさんの顔にしだいにズームしてゆく。明るい陽光を透かした髪がふわふわと風にそよぎ、目をかすかに潤ませ、口の中のものをゆっくりと呑みこみ、最後に深々と溜息をつく。ショットが切り換り、おばさんの右手前方の少し引き気味の位置からカメラがプラタナスの巨木を真正面に捉えたかと思うと、ゆっくりと流れるように湖面の方へとパンしてゆく──「その時、私はパリを愛しはじめていました。そして同時にパリが私のことを愛していると感じました」。僕はこのシークエンスを見ながらそくそくと迫ってくる感動に胸をつまらせたし、垂れ下がった喉もとを嚥下のために動かしている、到底美しいとはいえないおばさんのクロースアップを見つめ思わず目を潤ませもした。プラタナスの根元のベンチには、白黒のぶち犬を膝にちょこんとのせた初老の男性が腰を掛けているのだけれど、その犬までもが、かがよう湖面をきっと見つめているはずだ──そんな気にさせるシークエンスだった。
知らないものを思い出すように何かを思い出すこと。そして喜びと悲しみにひとしく貫かれながらまざまざと生きていると感じること──「懐かしさ」とはこう定義できるような気がした(そもそも「知らないものを思い出す」とは、映画といわずあらゆるミメーシスの本質ではなかろうか)。というより、そんな定義はさておき、そこにプラタナスの木があったこと、その不意のイメージの訪れに「懐かしさ」の機微がそっくり秘められている気がする。この短編を教材にどんな授業をしたものかと今考えている。