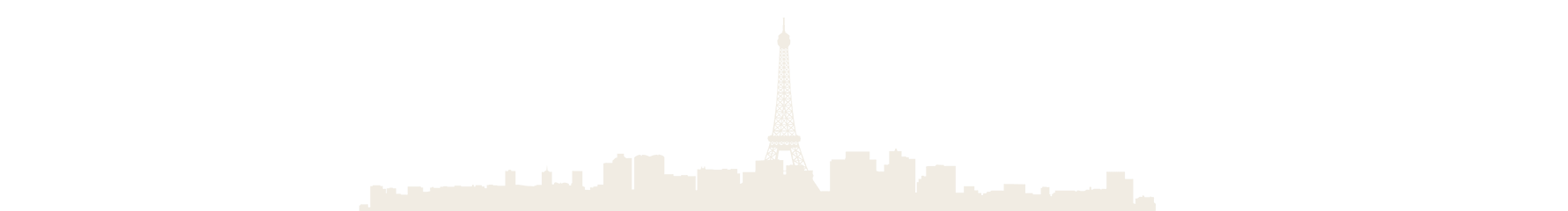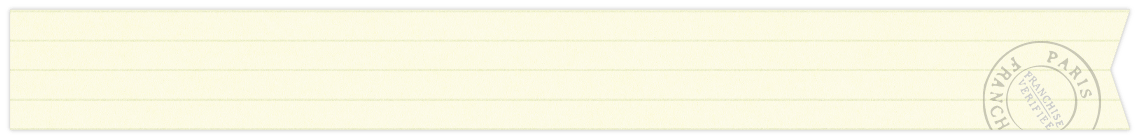
「目白バ・ロック音楽祭」礼讃
今回の音楽祭でガッティとならんで期待が大きかったのは、モンテヴェルディ演奏では世界最高峰との定評を得ているラ・ヴェネシアーナという声楽アンサンブルである。
このイタリア・バロック音楽の最大の巨匠にかんしては、まずその多声マドリガーレ作品をルーリーやカークビーらのイギリス人演奏家による精妙なガラス細工のような録音で知った。その後、アルノンクール指揮チューリッヒ歌劇場の「オルフェオ」をはじめとする画期的なオペラ上演を収録したLDのシリーズを買い求め、またガーディナーが御当地ヴェネツィアの聖マルコ大聖堂に乗り込んで演奏した最高傑作「聖母マリアの夕べの祈り」も熱中して聴いてきた。だがこうしたモンテヴェルディ理解を根本から覆すことになったのは、天才アレッサンドリーニ率いるコンチェルト・イタリアーノが来日した折りのコンサートだった。北部ヨーロッパの知的エリートたちによってあまりソフィスティケートされすぎたモンテヴェルディ像に、南方の太陽と土地の伝統に根ざした熱く神秘的な肉体性を回復してやったのが彼らイタリアの新興団体だったのだといまにして思う。そして、アレッサンドリーニの独裁的な暴君ぶりに反発してコンチェルト・イタリアーノから分派した声楽家たちを中心に結成されたのがほかならぬラ・ヴェネシアーナであり、いまやその実力は「本家」を越えたといわれるほどである。
今回の初来日にラ・ヴェネシアーナが持ってきたプログラムは、モンテヴェルディの「聖母マリアの夕べの祈り」とならぶ代表的な宗教曲集「倫理的・宗教的な森」からの抜粋を他の同時代の作曲家たちの作品をまじえた典礼形式でやるというもの。伴奏の小オーケストラのリーダーをガッティがつとめるというなんとも贅沢な趣向もあった。
会場の東京カテドラル聖マリア大聖堂には戸山キャンパスでの授業が終わったあと、散歩がてらのんびりと徒歩で行った。大隈会館を通って、神田川を渡り、椿山荘の庭園をのぼりきると、すぐ目の前に丹下健三の設計により1964年に建てられたステンレス・スチールとコンクリートからなる異様な構造物が現れてくる。外側は現在改装中で全貌をつぶさに眺めることができないが、内部に入るとコンクリート打ち放しの粗野な壁にぐるりを囲まれたそのだだっ広い威圧的な空間に圧倒される。祈りの場というより、なにかファシストの巨大な集会場を想起させる殺伐としたスペースだ。
正直いって教会でのコンサートはあまり好きでない。舞台が見にくいうえに椅子は狭くて固いし、天井の高い石造りの会場の音響特性(残響時間が長すぎる)のせいで、大編成の合唱曲など力いっぱいに演奏されようものなら、四方八方から音がごちゃごちゃに混ざり合って、自分が何を聴いているのかさっぱり分からないというようなありさまになる。事実、この数日前に同じ会場で日本の古楽グループによって行われた「聖母マリアの夕べの祈り」の演奏に対してはインターネットのサイト上にそのような不満の声が寄せられていた。
ただこの日のラ・ヴェネシアーナは最精鋭6名に絞り込まれ、共演の器楽陣も8名という小編成だったので、この点についてはなにも心配していなかった。むしろ危惧したのは、こんなわずかな人数の歌手の声だけでこの広大な空間をすみずみまで満たすことができるのかということだった。しかし、演奏がはじまり、信じられないほど澄みきったソプラノの声が礼拝堂のはるかな天井の高みへと駆けあがりはじめた瞬間にそうした危惧も吹き飛んだ。たったひとりのソプラノが大聖堂の重々しい威圧を造作なく押しのけ、さらにアルト、テノール、バスが十分な強度をもって重なり合い、そこに弦楽器群の柔らかな響きとハープやチェンバロの軽快なリズムが加わることで、異次元の音響世界が一挙に立ち上がった。ラ・ヴェネシアーナの声楽家たちの唱いぶりは男女問わずみなしっかりと野太くドスがきいていて、ときに荒々しく聞こえることさえある。イギリスやフランスの第一線の声楽団体のスタイリッシュな唱法に慣れ親しんできた耳にはひょっとして違和感が残るかもしれない。だが、モンテヴェルディの創始したバロックという新様式は、まさにこのような明暗の対比のくっきりした、激しくドラマティックな表現をもともと要求していたはずなのだ。気がつけばもうかなりの長さになる自分の古楽遍歴をふりかえりながら、ついにモンヴェルディ演奏の原点に立ち会えたという満足感にひたりきることのできた一晩であった。
古楽愛好者たちのブログを見るかぎり、今年の目白バ・ロック音楽祭は無理をしても聴きに行っておけばよかったなと残念がらせるような演奏会が他にもいくつかあったようだ。年とともに熟成を重ねて、ますます内容を充実させてきたこの音楽祭、来年の6月も未知の音楽と新しい演奏家との出会いを求めて、目白の街にたびたび足を運ぶことになるであろう。