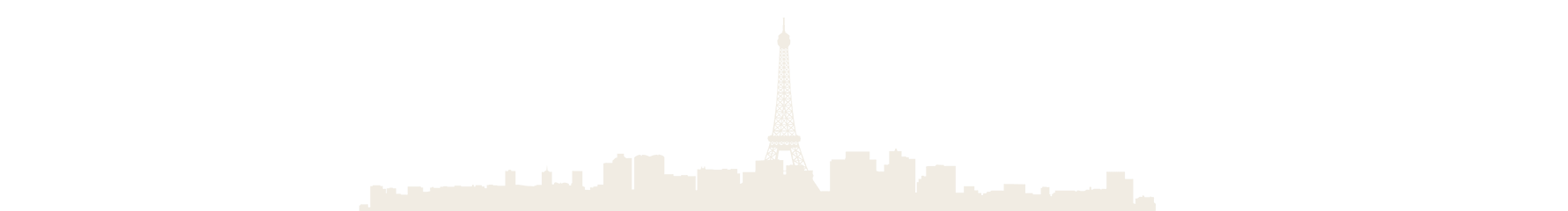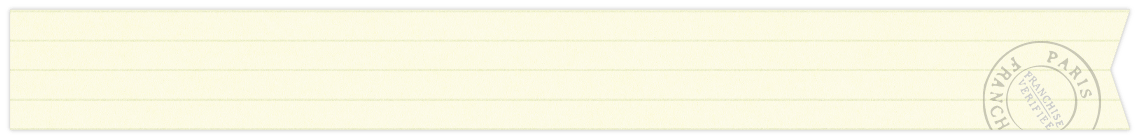
「目白バ・ロック音楽祭」礼讃
川瀬 武夫
毎年6月になると、早稲田からほど近い目白の地でバロックを中心とした、いかにも手作り感のある音楽祭が4週間にわたって開かれる。主催者側の説明によれば、目白という「場」に「ロック」な人々が集い交流するのが開催理念ということだが、ヨーロッパの17世紀から18世紀にかけての古い音楽を好んで聴きに来るのがどうして「ロック」な連中なのかてんで意味不明なまま、一方でたんに学習院や日本女子大があるなとしか意識してこなかったこの街の「山の手」的な奥行きを再発見するのに、なるほどうってつけの機会となる。具体的には、ふだんあまり訪れるチャンスのない、東京カテドラル聖マリア大聖堂、目白聖公会、聖母病院チャペル、日本女子大学成瀬記念講堂、自由学園明日館等々の、この地区に点在する由緒ある歴史的建造物が会場となっているのがこの音楽祭の売りのひとつなのである。
3年目にあたる今年は前半が「モンテヴェルディ・フェスティバル2007」と特集されて、本場イタリアからバロック・ヴァイオリンの名手エンリコ・ガッティと超絶技巧の声楽団体ラ・ヴェネシアーナが初来日を果たすというので、早くからチケットを予約して公演の日が来るのを楽しみにしていた。
最初に行ったのはガッティがイタリア・バロック期のソナタを弾くリサイタルで、会場は目白の隣の池袋にある立教大学第一食堂。これは1918年に建てられたという重厚なイギリス様式の煉瓦造りの学生食堂で、入り口に掲げられたラテン語は「欲望は理性に従うべし」という哲学者キケロの言葉とのことである。リサイタルはその入り口を開け放しにして、初夏の爽やかな微風が満員の客席(250席)のあいだを涼やかに吹き抜ける環境で行われた。
イタリア系のバロック・ヴァイオリニストといえば、ビオンディ、オノフリ、カルミニョーラといった「鬼才」たちの、いずれも鋭くエッジの立ったケレン味たっぷりの「過激な」古楽演奏に久しく熱狂してきたものだが、ガッティの奏でる最初の楽音が聞こえたときから、この温厚な顔立ちの演奏家のめざしているのがまったく別のものであることがただちに直観された。それは一体どういったらよいのか、刺激臭の一切ない、芳醇でまろやかな、まるで蜜の味のような音色だった。モダン、ピリオドを問わず、これほど気品に満ちた甘美なヴァイオリンの音を聴いたことがないと思った。その分(というべきか)、運弓のミスや音程の乱れなどテクニック上の意外な脆弱さも露呈しながら、チーマ、フォンターナ、ウッチェリーニ、スピッサティ、ヴェラチーニら、CDですらめったに聴くことのできない作曲家たちのヴァイオリン・ソナタ群があくまでも繊細に淡々と演奏された。はじめての奏者とはじめての楽曲との幸福な出会いがあり、会場の独特な雰囲気ともあいまって、音楽の理想郷が一瞬そこに現出したような感覚にとらわれた日曜日の午後だった。
ガッティはもう一日、同じくイタリアのバロック・コンチェルトのコンサートを聴きに行った。会場が江戸川橋そばのトッパンホール(400席規模の小さいけれど最新のコンサートホール)だったこともあって、これはもっと「普通の」演奏会で、彼のパーフォーマンスもよりくつろいではるかに安定感を増していた。お約束のヴィヴァルディは優美で聴きやすくべつに悪い出来ではなかったものの(この過剰な作曲家については、やはりビオンディを実演ではじめて聴いたときの衝撃が忘れられない)、この日もむしろガルッピ、ボンポルティ、タルティーニといった「マイナーな」作曲家の珍しいコンチェルトに心がときめいた。イタリア・バロック期のヴァイオリン音楽という無尽蔵の宝庫から手品のように次々と繰り出されてくる隠れた逸品に耳を傾けながら、地中海のどこまでも晴れわたった青空にいざなわれる思いがしたものだった。