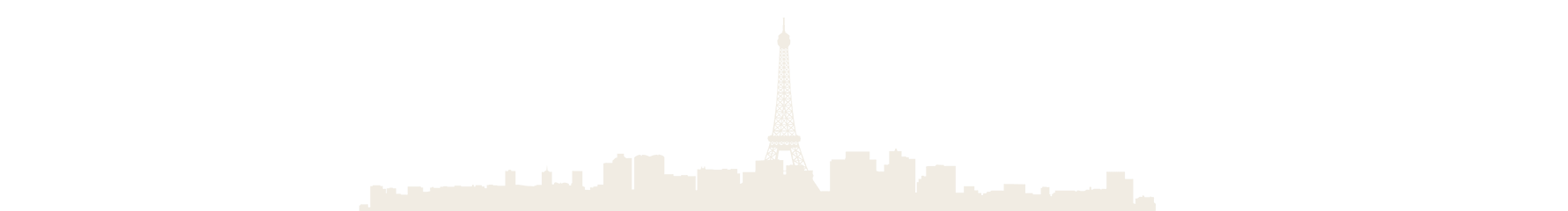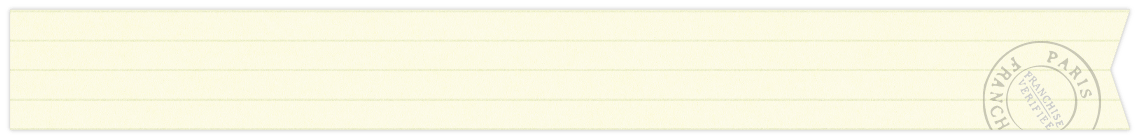
『シュルレアリスムと美術』展(横浜美術館 2007年9月29日~12月9日)
鈴木 雅雄
会期末が近いのですが、横浜美術館で開催中の『シュルレアリスムと美術──イメージとリアリティーをめぐって』と題された展覧会についてレポートします。これを読んでいくらかでも興味を持ってくれた人は、もうあまり時間がありませんが、足を運んでみてください。
具体的な情報は、以下のページを参照してください。
http://www.yaf.or.jp/yma/
国外のコレクションから借り出したものもあるとはいえ、この展覧会は基本的に、宇都宮美術館、豊田市美術館、横浜美術館の3館が所蔵する作品によって構成されたものであり、日本の美術館の収蔵品だけで、シュルレアリスムとして括られる領域の全体像がともかくも捉えられるというのは、やはり驚くべきことだといえるだろう。とりわけ横浜美術館は開館以来シュルレアリスム美術を積極的に紹介してきており、常設展示でもつねにひと部屋はこの系列の作品にスペースが作られているほか、マッソンとマッタを抱き合わせにした展覧会や、とりわけ見事なウィフレド・ラムの展覧会などで実績を残してきた。今回も125点の出品作品のうち実に半数以上は横浜美術館の収蔵品だが、今回展示されているものも所有する作品の半分に満たないという話で、この分野の収蔵品は日本のなかでは群を抜いた量であることを実感できる。
全体は、「シュルレアリスム以前」、「シュルレアリスム」、「シュルレアリスム以後」という3つの大きなセクションに分かれており、中心となる第2部はさらに7つの小セクションに分割されている。第2部の小テーマのなかには、「女と愛」、「神話と魔術」といった主題的なものだけでなく、マッソンやミロのオートマティックな傾向の強い画面、エルンストのフロッタージュ、ドミンゲスのデカルコマニーなどを集めた「イメージが訪れる」、エルンストのコラージュ=ロマンの図版を中心に構成した「反物語」、しばしば指摘される通りシュルレアリスム絵画のなかで重要な役割を果たす地平線の問題を捉えようとする「風景」などのセクションがあり、単に不可思議なイメージの集積というだけでなく、より構造的・方法論的な次元でシュルレアリスムを考えようとする姿勢が読み取れる。
ダリやマグリットといった特に認知度の高い画家、あるいは日本にマニアックなファンの多いベルメールの前で立ち止まる来場者が多いのはいたし方ないが、まったく個人的な趣味でいえばやはりラムの大画面は圧倒的であり、常設でも展示されていることの多いエルンストの《少女の見た湖の夢》のなかに、今まで気づかなかった愛らしい動物たちをまたいくつか見つけることは、やはり何といっても楽しい。またコーネルのボックス・コンストラクションが2点出品されているが、写真複製で見るとしばしばお洒落なインテリアといった印象を与えてしまうコーネルの作品も、実物はむしろかなりくすんだ色合いで違和感がなかった。実はこの展覧会の関連企画として(美術の専門でもない人間がそんなことをしていいのかと思いながらも)シュルレアリスム美術についての講演をする機会があり、その折にカタログにも論文を書いておられる学芸員の中村尚明さんに会場を案内してもらえたのだが、そのときに今回の展示では、コーネルの3点がすべてエルンストと隣り合って配置されていることを指摘され、何かとても納得した。30年代のコーネルのコラージュを見ると、彼にとってエルンスト体験がいかに決定的だったかを再確認できるし、《ソープ・バブル・セット:コペルニクスの体系》とエルンスト70年代の《形状》を並べてみると、シュルレアリスム美術という輪郭の定まらない領域を貫く常数のひとつが、何らかの「図」のようなもの──ここではそれは太陽系や地球の構造を示す図──への関心であったかもしれないと感じることができる。重要なのはおそらく、不可思議なイメージを見せようとすること以上に、自身の体験している伝達しがたい不可思議さを、何とか図解しようとする意志なのかもしれない。
また今回の展覧会では、企画展の展示室だけでなく美術館全体がシュルレアリスムというテーマで統一されている。常設展示の部屋に入っても、ミロとデルヴォーの連作版画が大きなスペースを占めているし、写真展示室も「シュルレアリスムと写真」と題されていて、マン・レイやケルテスなどだけでなく、シュティルスキーのように、おそらくあまり目にする機会のない作家の写真も見つけることができる。中央の階段を囲んでいるのも、ダリ、マグリット、ミロ、マッソンらの彫刻作品である。
たしかに運動を代表する画家のなかで、ジャック・エロルドやヴィクトル・ブローネルが欠けているのは残念だが、レオノーラ・カリントンやレメディオス・バロなど最近では日本でも認知度の上がった女性画家たちがきっぱり不在なのも、(収蔵品の都合もあるだろうが)フリーダ・カーロの人気に乗じたりしないという意味では潔く感じられる。むしろ考えさせられるのは、第二次世界大戦以後にパリ・グループに接近あるいは加入したような画家が実際上まったく含まれていないことで、日本における受容のあり方の問題でもあるだろうが、シュルレアリスムの美術史的位置づけの曖昧さあるいは困難さを実感せずにはいられない。いい方を換えると、この展覧会の第2部と第3部の関係をどう考えるかという問題でもあるだろう。シュルレアリスムがイメージの持つ力を再発見し、のちの画家たちがそれを多様なやり方で利用していったという考え方が間違っているとは思わないが、その利用の様態は何ともつかみがたいものだ。しばしば取りざたされる抽象表現主義との関係を、この文脈ではどう考えたらいいか。40年代以降もそれなりに同時代の美術──たとえばポップ・アート──に一定の注意を向けながら進められていったシュルレアリストたちの造型表現を、どの程度どんなふうに評価したらよいのか。いやそもそも、イメージという、美術批評においても文学研究においても、無批判に使うことは久しい以前から不可能になっているこの語彙に、本当のところどんな内実を与えるべきなのか、それを考えることはおそらく、シュルレアリスム美術とは何かについて考えることとほとんど同義であるかもしれない。