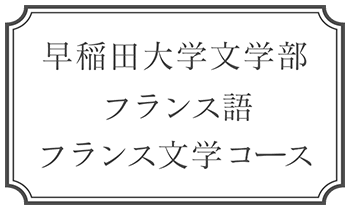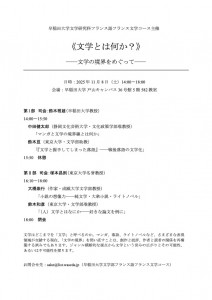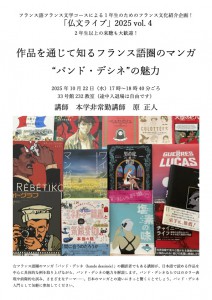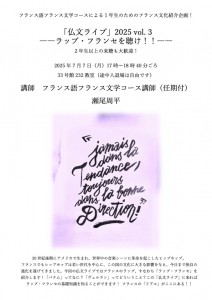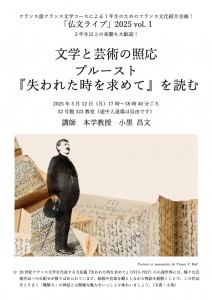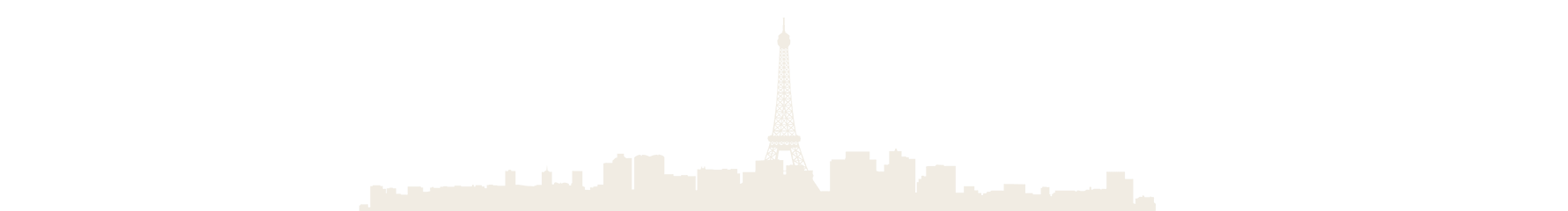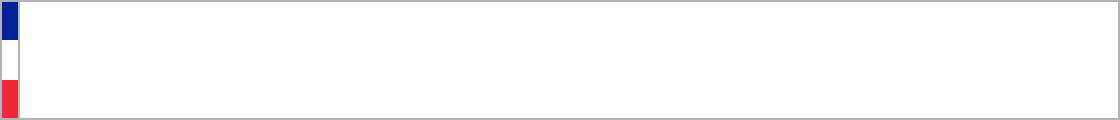
「仏文ライブ」2025 vol. 5, 11月17日(月)17時~18時40分
フランス語フランス文学コースによる1年生のためのフランス文化紹介企画!
「仏文ライブ」2025 vol. 5
2年生以上の来聴も大歓迎!
シュルレアリスムと映画
―芸術と大衆文化の関係を逆転させる-
2025年11月17日(月)17時~18時40分ごろ
33号館232教室(途中入退場は自由です)
講師 本学教授 鈴木雅雄
☆20世紀最大の文学・芸術運動とも言えるシュルレアリスムは、映画とどんな関係を取り結んでいたのでしょうか。シュルレアリストたちが熱狂したのは、難解で実験的な映像ではなく、『ファントマ』や『吸血ギャング団』といった、大衆的な連続映画でした。そこにあるのは、前衛的な芸術家が大衆文化からインスピレーションを得て作品を制作するといった、ありきたりの事態ではありません。複製技術が急速に発展した時代においては、大衆的なメディアこそが重要であり、新しい感性や思考の担い手なのではないか。そんなふうに考えた、1920年代のシュルレアリストたちに視線を向けてみましょう。そこには私たちが取り逃がしてしまいがちな、もう一つのイメージの歴史が見つかるかもしれません。(文責・鈴木)