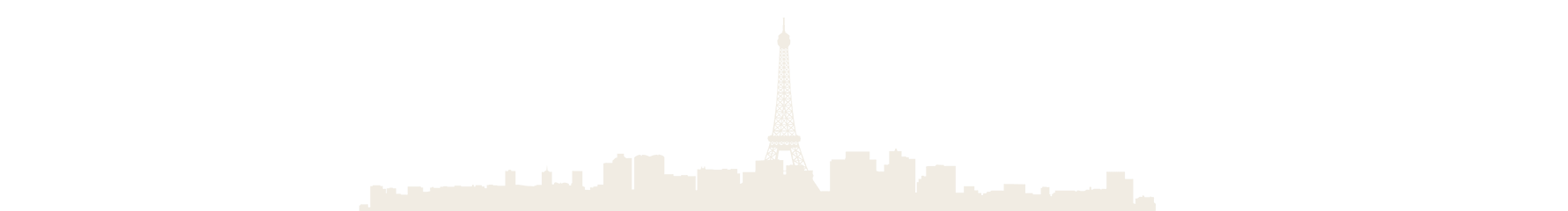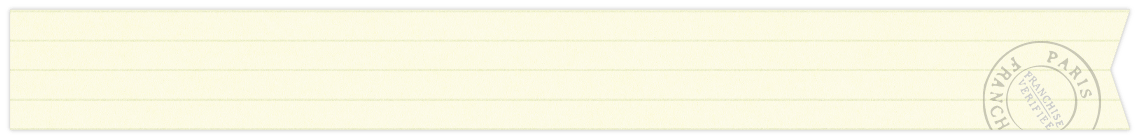
エドゥアール・ブーバの写真について
瀬戸 直彦
フランスの写真家のなかで私のもっとも愛する人といえば,この人である。1999年にEdouard Boubatが76歳で亡くなったとき,日本ではほとんど報道されず,『アサヒカメラ』誌がわずかに追悼の作品を4ページほど載せただけだったと記憶している。ブーバを知る人はその写真を甘いというかもしれない。しかし,フランスの,パリの,そして世界のあちこちの市井の人を撮りながら,これほど力強い,それでいてしっとりとした印象をあたえるのは,私にとっては,かれの作品をおいて他にはない。女性のポートレート,公園で遊ぶ子供,何気ないパリの,そしてフランスの田舎の風景,ポルトガルの海岸の抒情性,どれをとっても美しい。ただ美しいというのではない。しっとりとした,とでもいうしかない,何とも形容しがたい魅力にあふれている。同時代の有名な写真家,アンリ・カルティエ=ブレッソンのように決定的瞬間をねらうわけではない。ウイリー・ロニスのようなユーモアのあるパリ風景というのでもない。イジスの撮るノスタルジックなパリの記憶でもない。あらゆるメッセージを排していながら,なんともいえない芸術性のオーラ,抒情性のもつ力強さを発散しているのうに感じるのである。
リュクサンブール公園での「初雪」(1955年)。かたづけられ重ねられた公園の鉄の椅子を前景にして,男の子たちが真っ白の雪の上で遊んでおり,背景に東屋と垂直の木々のある写真はどうだろう。モンマルトルの街路の崩れた壁の前にたたずむ少女(1964年)。大きな靴を履き,薄汚れたコートを着た女の子の顔は,この子の先の人生をすでに語っているかのようだ。ニューヨークの「ブルックリン橋」(1982年)。林立した高層ビルを背景に,左上から斜め右下に幾本もの綱が支えている橋の上のすばらしい構図。綱に手を支えて遠くを眺める女性の倦怠感をたたえた後ろ姿。また,日本の幼稚園のなかで,帽子をかぶり制服をきた女の子たちの一団を撮った作品(1987年)。中央の女の子のりりしさはどうだ。あるいは地方都市「バルブジユー」Barbezieuxの一光景(1956年)。お偉方だか選挙に出る候補者だかが,芝生にしつらえたフランス国旗のはためく演壇の上で,真昼間に大真面目に演説している。大人たちはそれを傾聴しているのに,演壇のすぐ横では子供たちが遊び,右前では女の子2人がお喋りに夢中である。モノクロでとらえた永遠の瞬間ではないだろうか。
ブルターニュの海岸で撮った「レッリャ」Lellaという作品は,2年間一緒に暮らしたイタリア系女性の一種のポートレートで,ブーバの写真でもっとも知られた作品のひとつであろう(1947年)。海辺の風に髪をなびかせ黒い下着に薄物をまとった若い女性が右の方向をきっとした様子で眺めている。このばあい,きりっとしているのでもなく,凛としているのでもない。きっとしているのである。モノクロ写真のしまった黒とよく抜けた白が強調され,女性の真の強さと美しさがこれほど力強く表現されている写真を私は見たことがない。ところで,この人の作品集が始めて単行本として出版されたのが日本であったということも,記憶しておくべきことであろう。ポルトガルはナザレの海岸のカラーによるルポルタージュ『海の抒情 Ode maritime』(平凡社,世界写真作家シリーズ,1957年)である。ブーバのカラー写真はめずらしい。しゃれた装丁は原弘で,序文が伊奈信男,フランス語によるBernard Georgeの解説には林達夫の翻訳が付されている。
ここに転載できないのが残念だが,このLellaは,新潮社の「とんぼの本」シリーズの『写真の見方』(細江英公・澤本徳美著, 1986年)の55ページに見ることができる。ブーバの仕事の全体像をかんたんに知るには,フランスのポケット版写真家シリーズ,photo pocheの第32巻,Edouart Boubat(1982年)をお勧めしたい。Lellaをとった一連の写真は,その50年後に彼女の回想を付した小冊子が出ている(Edouard Boubat, Lella, Paris Audiovisuel / Maison Européenne de la Photographie, 1998.)。ほかにMichel Tournierとの共著:Vues de dos, nrf, Gallimard, 1981.も入手しやすい。写真術についてブーバの語ったLa photographie, l’art et la technique du noir et de la couleur, Livre de poche, 1985.もたいへんに面白い。じぶんの作例の解説と使用機材についても書いてある。たとえば「ブルックリン橋」はLeicaのM3, Summicronの50ミリを使ったことがわかる。この本を読むと,この写真家が文章のうえでも詩人であることがわかるであろう。
トピックというコラムは,現在みられる展覧会などの紹介が主眼らしい。ブーバの作品は,残念ながら日本ではげんざい,ほとんど公開されることがない。そのときどきの話題性とは無縁である。2004年に亡くなったアンリ・カルティエ=ブレッソンはそうではない。ブーバとおなじく主として1950年台にフォト・ジャーナリストとして世界各地を回り,またパリを写真に収めてきたブレッソンは,つねに巨匠の名をほしいままにしてきた。めずらしくも本人がプリントしたものも含めて,本年(2007年)8月12日まで,東京国立近代美術館で展覧会が開催されている(「アンリ・カルティエーブレッソン-知られざる全貌」)。ブーバについても,いつかは日本で本格的な写真展の開催される希望をこめて,この稿をしたためました。