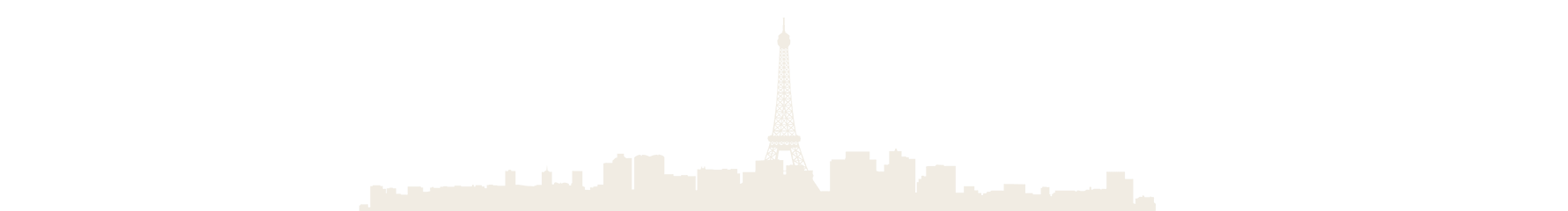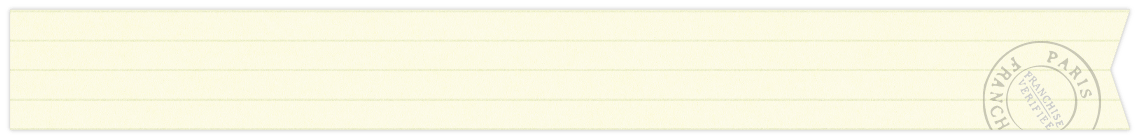
Que reste-t-il de nos amours ?
昼間 賢
表題は、往年のシャンソン歌手シャルル・トレネの名曲で、その意味をまずは直訳で捉えていただきたい。「ク~レ~スト~ティル、ドゥノザムール、ク~レ~スト~ティル、ドゥノザムール」と繰り返すトレネの歌い方は、懐古的な歌詞に合わせて寂しそうではあるが、その声色は、むしろ明るい。この歌が生まれたのは1942年、つまりパリは占領下で、だからこの明るさのわけが気になるのだけど、シャンソンに詳しい方にとっては、トレネは何を歌っても明るい、それだけのことかもしれない。「よろこびのうた」だって暗い時代の歌だよ、こっちのほうがずっと輝いてるじゃないか。にもかかわらず、その明るさはどこか装った感じがする。実際には「よろこびのうた」は戦争前の歌で、次第に暗くなってゆく時代を明るく乗り切ろう、という調子の、無頓着というか、強がりというか。かえって虚しくなるような白々しさでさえある。「残されし恋には」の明るさは、それとは違う。いわば、残余の光。たゆたえども沈まなかったものの煌めきだ。
僕がフランスのポピュラー音楽に目覚めたきっかけは、1993年、当時早稲田で教えていたパトリック・ルボラール氏の授業中に聞かされたMCソラールのデビュー作だった。曖昧模糊と聞こえていたフランス語の中を、軽快な嵐がさっと吹き抜けるようだった。その衝撃で、そのころ流行っていたネグレス・ヴェルトのカッコよさ(特にセカンドの)がわかるようになった。前者はラップ・フランセの先駆け、後者はミクスチャー・ロックの金字塔である。実は、同じ時期にトレネも聞いているのに、どんな感想を持ったかは全然覚えていない。それから五年後、到着したばかりのパリで、留学中の指導をお願いしていたアントワーヌ・コンパニョン氏の新刊書『理論の悪魔』の序論にこのタイトルが使われていて驚いたことはよく覚えている。授業では「プルースト研究なんてもうやめましょう」などと言い放つ先生で、一時期はずいぶん悩んだ。その言葉を相対化できるようになったのは最近のことだ。
とにかく、フランスのポピュラー音楽は僕にとって、最初から混ざりものとしてあった。僕より年上の人たちには思いも寄らない聞き方かもしれない。甘くささやくフレンチ・ポップスは、ほとんど知らない。当時亡くなったばかりで人気絶大だったゲンズブールも、後追いで聞いて感銘は受けたもののリアルな聴取体験にはなっていない。僕にとってのヴァリエテ・フランセーズとは、ネグレスやテット・レッドなどあのころは多かったバンド系と、実はMCソラールもその文脈で聞かれていたアシッド・ジャズ系のグループが中心で、少し後でゼブダが登場したころには、エールやフレデリック・ガリアーノなどエレクトロ系のサウンドも聞くようになった。僕自身が音楽活動に熱中していた(サックス吹いてました)ことも無関係ではなかった。音楽とは第一に鋭利なサウンドであり、歌詞やメッセージなんてほとんど関心がなかった。渡仏後も、伝統的なフランスらしさとは異質な音楽ばかり探し求めた。世紀の境目にあったフランスは、90年代前半に花開いた様々な音楽がそれぞれの最盛期を迎えていて、何を聞いてもおもしろかった。拙著『ローカル・ミュージック 音楽の現地へ』は、個人的にはその集大成のつもりだった。この本は、実は本文を書き終えてから案出したローカル・ミュージックというコンセプトが比較的目新しかったのと、予定より大幅に遅れた刊行が偶然にも2005年秋の郊外暴動と重なったため、好意的な読者には、新しい時代の、それも不穏な新しさを先取りしたものとして受け取られた。それはそれで嬉しかったが、僕自身は、騒動が鎮まるのを見届けた上で、ひとつの時代の終わりが刻まれた本ということになるだろうと感じていた。