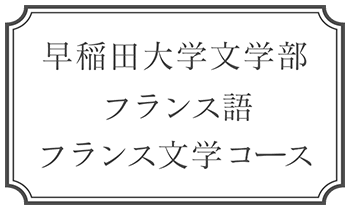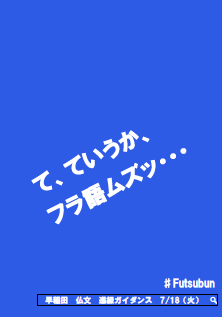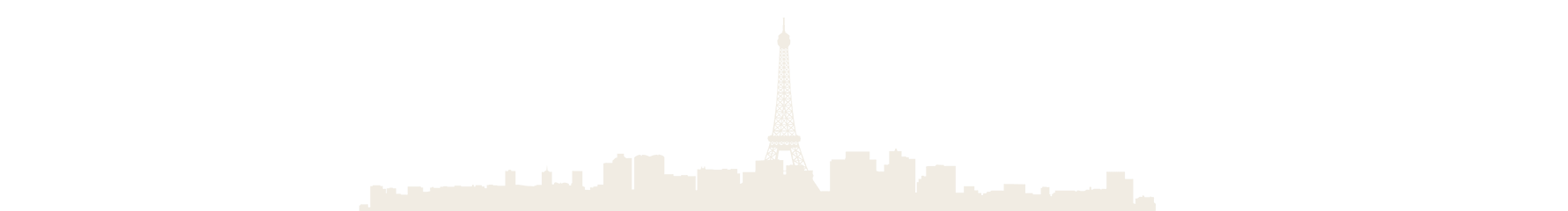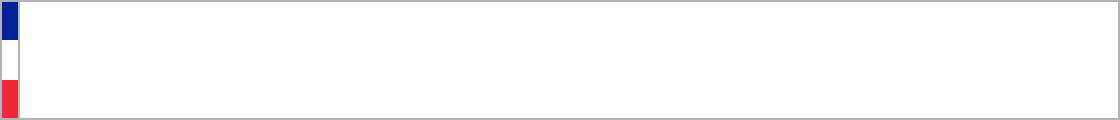
「フランス文化をやっつけろ!」vol. 3【11月1日(水)】
みなさま、
毎度お馴染みのシリーズ企画「フランス文化をやっつけろ!」
ついに第三弾がぶっ放されます!
今回の内容は・・・フランス・オペラをやっつけろ!
17世紀イタリアで発祥したオペラがフランスでいかに独自な発展をとげたか。 フランス・オペラの成り立ちと魅力を映像・音楽満載で語り尽くします!「オペラ」の「オ」の字も知らな〜いという方も大丈夫。「仏文の池上彰」の異名をもつ川瀬先生が丁寧にわかりやすく解説してくれますよ!
「フランス文化をやっつけろ!〜vol.3 : フランス・オペラをやっつけろ!〜」
・日時:11月1日(水)17:00〜19:00
・場所:フランス語フランス文学コース室(戸山キャンパス39号館3階)
キャンパス案内図⇒http://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2014/08/edb11e6c82861fa22b605950bcfdee00.pdf
・講師:川瀬武夫(本学教授):専門は19世紀フランス文学と近現代詩。詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。
・入場無料・来聴歓迎・お菓子&ジュースつき
公式ビラはこちら。みなさまのご参加をお待ちしております☆
早稲田仏文